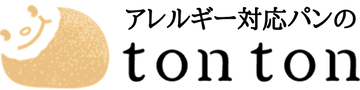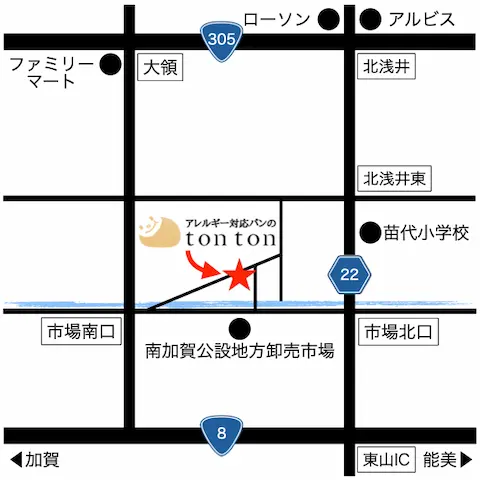みんなが安心して食べられる外食・中食を目指して

強い食物アレルギーがある子どもたちにとって、外食や中食は憧れですよね。
でも、それにつきまとうのが、「誤食リスク」という問題。
食品加工品にはアレルギー表示義務があっても、外食・中食には義務がないため、食物アレルギーを持つ人が安心して利用できないという課題があります。
食物アレルギーを持つ人々が外食や中食を安心して利用できない現状と、その背景にある課題。
消費者庁が啓発活動している動画がありましたので、ご紹介しますね。
知らないと取り残される!飲食店での食物アレルギー:消費者庁(外食・中食における食物アレルギーに関する情報提供の取組)
動画の主なポイント
外食・中食での「食物アレルギーの現状」を、実際の事例でわかりやすく紹介されています。
お客様・家族・飲食店の3つの立場から、よく起きる場面や困りごとが説明。
■ お店が取り組むべきことを、シーン別に具体的に紹介
- 対応できる範囲を決める
- 原材料や調理方法をどう伝えるか
- スタッフ全員で共通のルールを持つ
■ 「曖昧に答えない」姿勢が大切
- わからない時は「わからない」と正しく伝える
- 混入(コンタミ)の可能性は必ず説明する
- 最終的に食べるかどうかは、お客様自身が判断できるようにする
■ 業界全体で意識が高まってきている
- 法律で表示義務はなし
- 外食・中食全体で「対応意識が高まる」流れ
- 今は事業者・消費者が協力して「安全な情報提供の仕組み」を作っていく段階
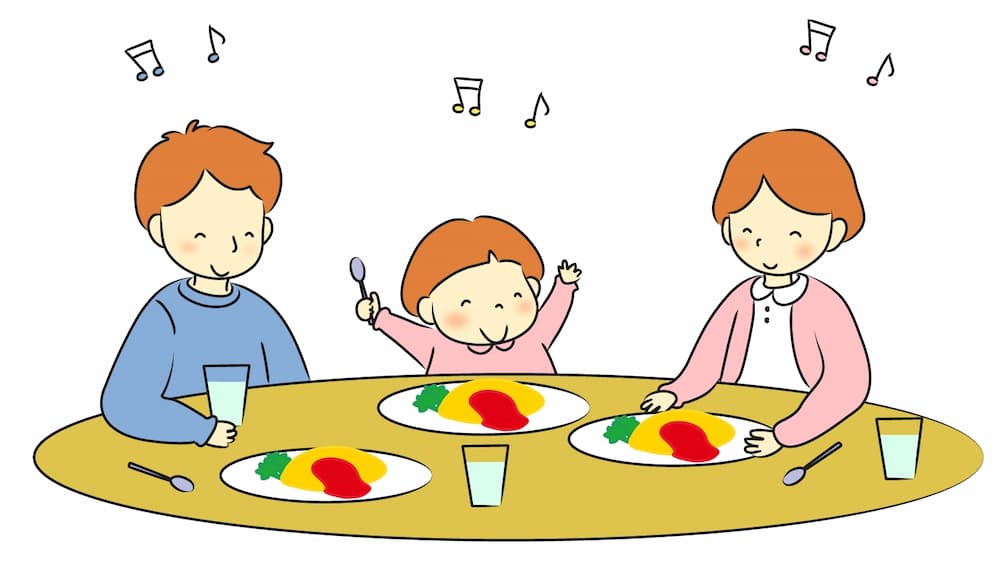
みんなが安心して食べられる社会へ
社会として理想的な取り組みとして、
- 教育の場で食物アレルギーへの理解を深めること
- 外食・中食全体で対応意識が高めること
- 外食・中食業界・消費者が互いに歩み寄ること
「誰もが安心して外食・中食を楽しめる社会」を目指すという提言をされています。
しかし現実には、事業者側の対応には大きな負担があります。
- 「アレルギー専用の厨房」でない限り、誤食が起きてしまうリスク
- 設備投資や従業員教育にかかる費用
- 「アレルギー対応」と大きく打ち出すことのリスク(味や印象への誤解)
トントンは1、2はクリアしていますが、3に苦しんでいます…
アレルギーで困っている方に喜ばれる反面、そうではない方には「きっと美味しくないよね」と思われてしまう…
悩ましい問題です…
外食・中食産業は厳しい経営環境にあるため、制度として一律に義務化すると、事業継続が難しくなる場合もあります。
まさに「安心と現実」のはざまで悩ましい問題ですが、どうやってお互いに安全と利便性を両立させていくのか。
みなさんのご意見をお聞かせいただけると嬉しいです。